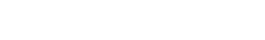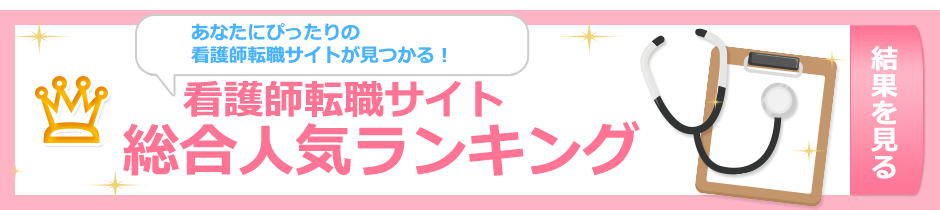色々な患者さん
看護師になってからも、ターミナル期の患者さんを担当することは、大変難しいことだと思います。ましてや学生の時分に、実習という小さな枠の中の限られた時間でターミナル期の患者さんを受け持つことは、困難極まりないことです。しかし看護師になる過程で避けては通れない道であり、その先の自分の看護観や自身の人生などについて、必ずや考えさせられる経験となることは間違いありません。学生時代のそんな貴重な体験のお話です。
子宮がんを患った50代の女性を受け持ったときのことです。私が出会ったときはすでに腹腔内全体にがんが広がり、手術の施しようもない状態でした。抗がん剤も効果は望めず、疼痛緩和のケアを中心に日々を過ごしていました。気丈に痛みと戦っていましたが、下血と嘔吐、腹痛がひどく、24時間モルヒネの持続点滴を行っているせいで意識も朦朧としがちでした。私にできることは排泄や清潔の介助と、少し調子の良いときに患者さんの好きな洗髪を行うことと、車椅子での散歩くらいでした。
約一ヶ月でひとつの実習を終えるのですが、3週目あたりから患者さんはほとんど日中を寝て過ごすようになりました。洗髪や散歩の計画を立てるも実行できず、ほとんど会話もできずに一日が終わることもありました。しかし学生の身分としては、何か援助できることはないかということが気になり、一日中何もしないで実習時間が終わることがとても気まずく、申し訳なく思えました。
日々のレポートにその日行う援助の予定を書く部分があるのですが、私のレポートは予定を立ててもいつも計画倒れ、ずっと空白のままです。一体何をしたらいいのだろう、そう悩んでいた時、カンファレンスで担当教官にこう言われました。「彼女に一番必要な援助を、あなたは毎日しているわよ。なにもしないで傍にいることだって、立派な看護です。」 それを聞いたとき、自分が今まで焦って立てていた計画は、全く自分本位な援助計画で、看護の押し付けだったのではないかということに気づきました。ターミナル期の患者さんを前に、一学生にできることはないに等しいのです。それからは努めてそばにいて、患者さんが目覚めたときだけお話を聞くというスタイルでやっていきました。実習の終わる二日前の朝、訪室するとそこにはきれいに整えられたベッドがあるだけで、患者さんの姿はありませんでした。夜の間に容態が急変され、そのまま息を引き取られたそうです。
この経験を通して、自分が看護を通して患者さんの人生に関わらせてもらったのだ、という実感を覚えました。看護という職業は、生も死もそばにいて見届ける、ある意味特殊な職業です。死をいたずらに恐れたり特別視したりせず、あくまでもその人の人生の一環として捉え、最後のときまで個人の尊厳を重視する関わりを持ちたい。そう思いました。
色々な患者さん その2
患者さんとの出会いは、学生の頃の実習に始まります。まだ正式な看護師とも認められていない若くて頼りない学生を、快く引き受けてくださった患者さんの寛大さには敬服の思いでした。そのおかげで看護師になれたと言っても過言ではありません。もちろん学生を嫌う患者さんもいらっしゃいます。ご自分の具合が悪くて入院されているのですから、そっとしておいてほしいのは誰しも本音の部分にあると思います。実習を楽しくするも辛くするも、担当の患者さん次第(あと、担当看護師も・・)だったのを思い出します。そんな愛すべき患者さんとのエピソードをほんのすこしだけ綴ってみます。
肺がんの手術を目前に控えた、60代の男性患者さんを受け持っていたときのことです。口数は少ないけれどニコニコ笑顔の素敵な方で、抜けた歯と、鼻の頭が酔っ払いみたいにいつも赤いのが印象的でした。フラーっと個室からいなくなったかと思うと、戻るたびに煙草の匂いがしていました。術前だからだめですよ、と言っても「はいはい」と笑顔。そして「看護師さんには内緒ね」と私に言うのです。看護計画に禁煙指導を挙げてパンフレットを作り、指導をすると「よくわかりました」と言われましたが、5分後には部屋から出て行き、まさかと思うも戻ると又煙草の匂いが。悩んだ末看護師に相談すると、担当医も看護師も皆喫煙のことは知っていました。注意はしても、半ば容認という感じで見ていたそうです。そして「煙草は、彼にとって家族で、友達で、精神安定剤だからね。」と言われました。この方は情報によれば子供さんがおらず、離婚をされていて身寄りのない方でした。面会にやってくる人はほとんどなく、寂しさや手術・術後の不安を煙草で癒していたのでしょう。「肺がんの術前=禁煙指導」という図式が頭の中にあったのですが、この方にもっと必要なことは他にあったのです。それは胸中の不安を少しでも軽減すること。口数の少ない患者さんに嫌がられはしないか、と気にして訪室する回数も少なく、あえてお話をするための時間を取ろうとしませんでした。学生の自分には何が必要か思い及ばず、患者さんの役には立てませんでした。
無事に手術を受けられ、帰室されて気分はどうですかと尋ねると、「煙草が吸いたいです」と一言。苦笑しながらも、では早く元気にならないと、と言うとにっこりされました。その後はそばにいて色々な話をしました。手術を終えた安堵感からか、こんなに饒舌な方だったのかと思うほど、たくさんのことを話してくれました。本当は奥さんも子供さんも亡くされていて、今は一人身であること。煙草とは10代のころからの付き合いで止める気もないこと、等々。実習が終わるとき、挨拶に行くと「煙草は少し減らすように、努力します」と言ってくれました。患者さんの性格や本音の部分は少し接しただけでは理解し得ません。決め付けずにしっかりと向き合って、全体像からその人に必要なのはどんな援助かと、よく考えるべきだということを教わりました。